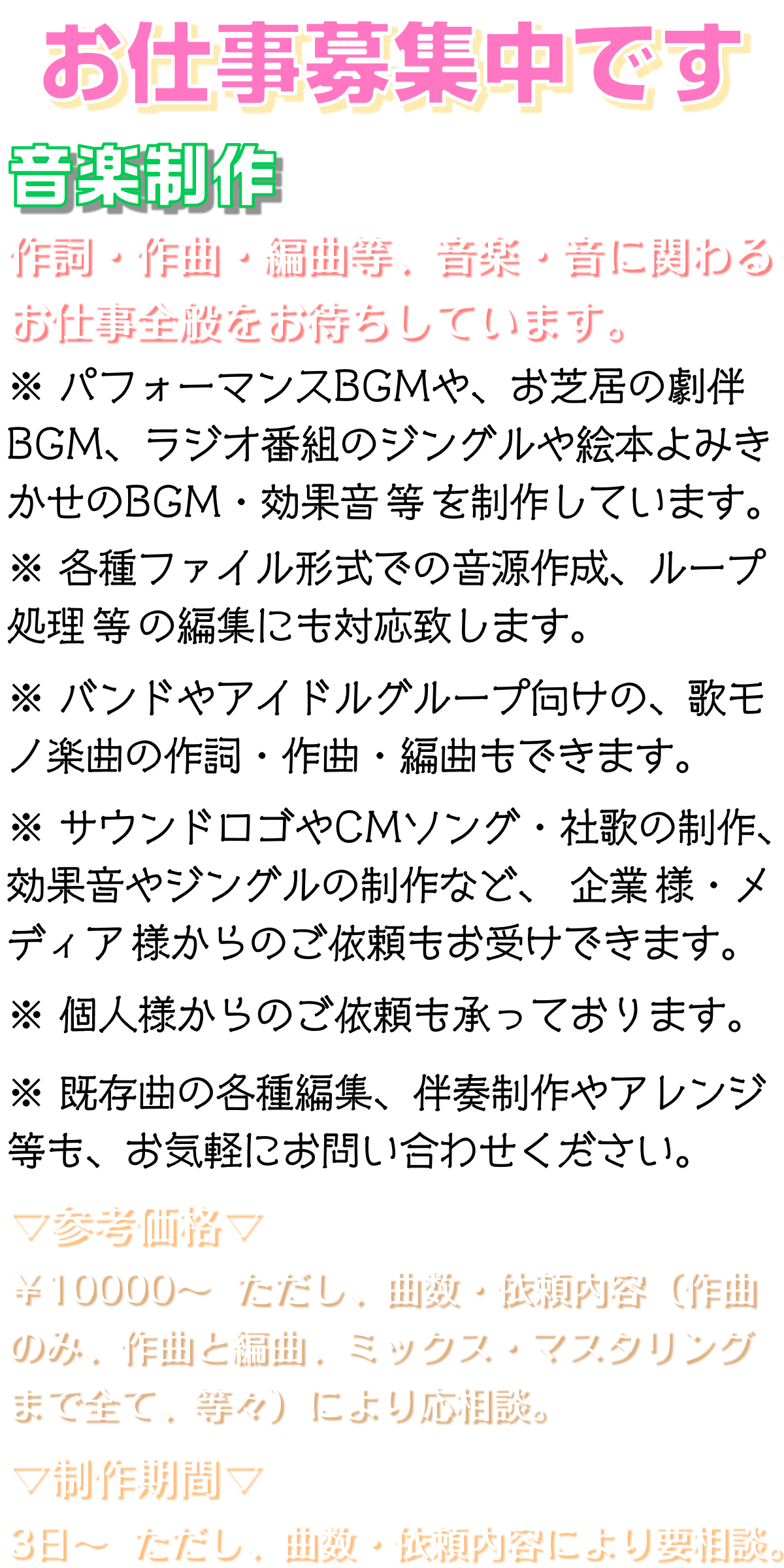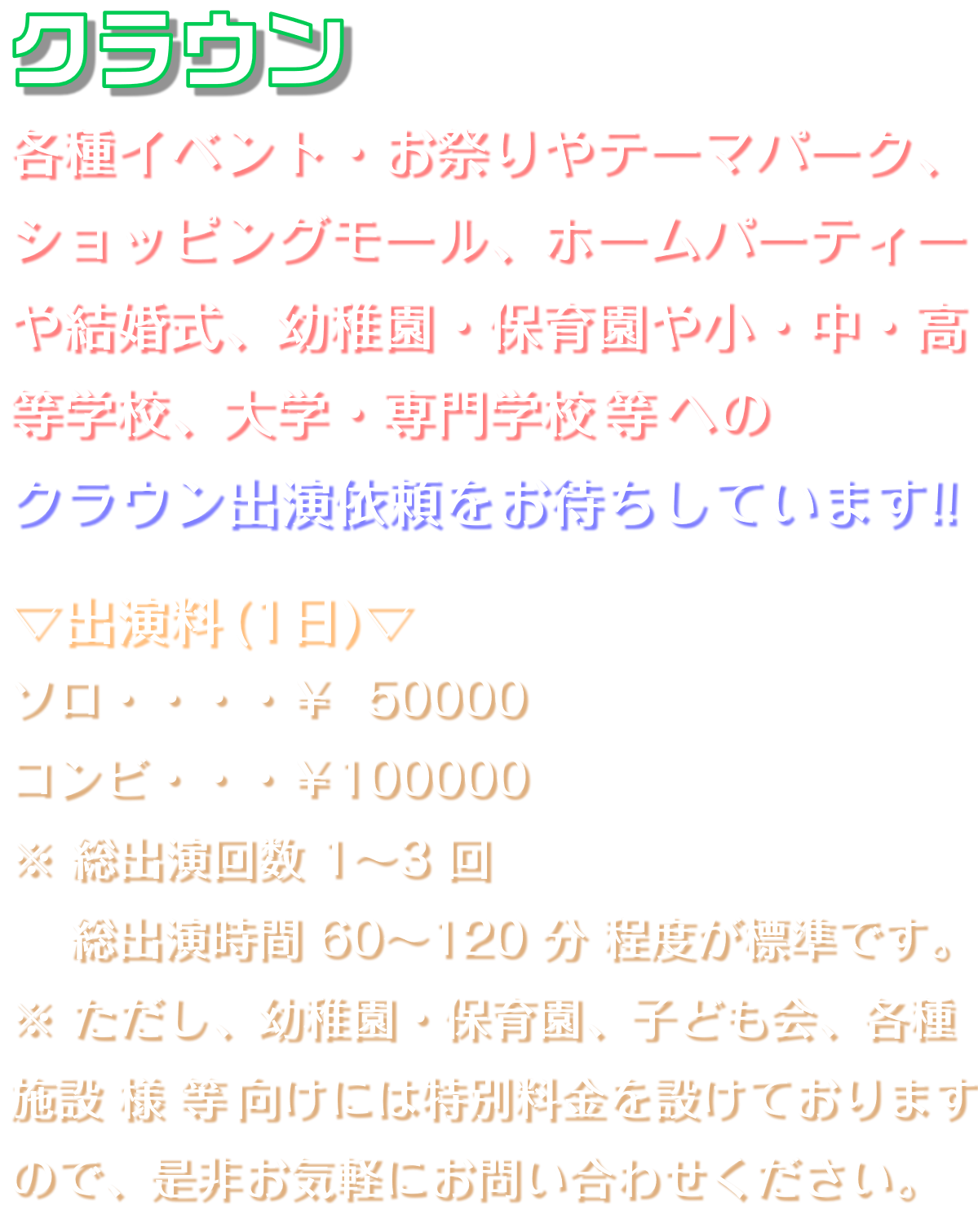てっぺん(小説)

てっぺん
いつの頃から、気がついてしまったのだろう。
かつて、確かに僕等は限りなく広がる自由の草原の只中にいた。
緑の海の波間をかきわけ、気ままに走り回っていた。
どこへも行けて、何にでもなれる・・・はずだった。
それなのに、いつの頃から、気がついてしまったのだろう。
背の高い草の下に隠れてはいるけれど、僕等の足元に確かに敷かれているレールの存在に。
まやかしの自由。
行き先は決められていた。
どこへも行けない、何者にもなれない。
縛られている感覚が嫌で嫌でたまらない。
レールから外れようと必死になって走ってみても、振り返ればそこは同じレールの上。
悪あがきは止めろと悪魔の囁き。
意地張って知らん振りを決め込む。
すると気づいた時には辺りは取り返しがつかない程暗くて遠い場所。
まるで下手に触れると余計に広がって手に負えなくなる傷口のようなもの。
そう、傷。
完全無欠、清廉潔白であったはずの僕等の人生に、少しずつ増えていく、傷跡。
子供の頃から絵を描く事が好きだった。
中学校に入ったぐらいから、他人より上手に描ける自分を自覚した。
高校時代は展覧会入選の常連だった。
しかしこれを才能と呼んでよいものかどうかを判定するには当時の私の絵画に関する知識は幼すぎた。
かといって、絵を描く事の他に情熱らしきものを抱ける対象は見つからなかった。
絵描きになろう、そう思った。
決心、というにはあまりに漠然としたものにすぎなかった。
確かになれるという自信はなかったが、無理だと諦めてしまう勇気も無かった。
美大への進学を決めた。
根拠は無いが、なんとかなるのではないか、と考えていた。
今になって思い返してみれば、それはまるで執行猶予のようなものではあった。
多分に洩れず、美大の授業はつまらないものだった。
モラトリアムとも言うべき甘っちょろいキャンパスライフは描きたいという衝動を掻き立てるには程遠いものだったし、かと言って、外部からの制約の全く無い生活の中に在って自分で自分を追い込める程ストイックな一面を私は持ちあわせてはいなかった。
ただただ時間だけが過ぎていった。
このままでは駄目だという危機感から、一年間大学を休学し、スケッチブックを片手に放浪の旅に出てはみたものの、結局手元に残されたのは、全く進歩の跡の見られない没デッサンの山と、言いようもない無力感だけだった。
この受け容れ難い現実を直視しておのずから苦痛を増幅させていただけの私を尻目に、利口で堅実な同輩達は、早々に見切りをつけるという賢い選択によって無難に就職口を決めていた。
それでも依然として絵に対するこだわりを捨て去る事ができずにいた私は、中堅どころの広告代理店に頼み込んで、なんとかデザイナーの肩書きで拾ってもらえる事になった。
しかしそれは単なる意地と取れなくもなかった。
デザイナーの文字を冠した自分の名が刻まれた名刺を眺めて安心した気持ちになっていたのも束の間だった。
所詮商業デザインはアートとはかけ離れたものだった。
絵心の『え』の字もわかっていないようなプランナーやディレクター達に、これまで自分が積み上げてきたものを悉く否定された。
広告とはいえ私にとっては大切な作品である。
その作品を否定される事は自分が生きてきた人生そのものを否定されるのと同じ事だった。
試行錯誤し、もがき苦しみ、それでも絵を捨て切れずにここまできた自分の人生の全てが無駄な時間だったと言われているような気がした。
名刺に刻まれたデザイナーの文字はそのままだったが、私にはデザインの仕事は全く回って来なくなった。
ちょうどよかった。
この頃には絵を描くどころか見る事さえもつらく感じるようになっていた。
代わりに与えられたのは営業職のポストだったが、とはいえその方面での力が人並み程度にあるわけもなく、私が任される仕事はといえば、誰が行ってもさして問題の起こる心配のない、小さな得意先との簡単で退屈な打ち合わせばかりだった。
子供の熱が引いていく様に、生半可な情熱やこだわりを自然に忘れていくためには充分過ぎるほどに刺激の乏しい毎日が続いた。
とにかく腹が減っていた。
面倒な雑用を全ておしつけられ、得意先を行ったり来たりして昼飯を食べる暇もなかった。
会社に戻る前に何でもいいから腹に入れておきたかった。
そのらーめん屋の暖簾をくぐったのは特に理由があったわけではなく、ただちょうど目に飛び込んできたというその一点のみであった。
『いらっしゃい』
客は私ひとりだった。
思わず腕時計を見るともう午後三時を過ぎている。
準備中だったかな、と踵を返しかけたが、いらっしゃいと言われたな、と考え直してゆっくりと歩を進めた。
一番奥のカウンターに崩れるように座り込む。
搾り出すように『らーめんひとつ』とだけ言うと低く頭を垂れた状態で木造りのカウンターの木目をじっと見つめたまま、どっと襲ってきた疲労にしばしの間顔を上げる事さえできない。
『このチャーシューどうですか』
元気のいい声に我に返って顔を上げると、カウンター越しにまだあどけなさの残る青年の店員が一人、包丁を持って立っていて、奥の店長らしき人を呼んでいるのが見えた。
『どれ、見せてみ』
どうやら、客の少ないこの時間に新入りの指導をしているらしかった。
店長は青年の手から徐に包丁を取り上げると、慣れた手つきで鮮やかに、ひとつの肉塊から一枚のチャーシューを切り取って見せた。
チャーシューを切る、ただそれだけの行為から、どうしようもなく惹きつけられる何かを感じた。
気持ちいいほどのその切れ味は一筋に何かを続けてきた人に特有の凄まじい集中力を具現化しているかのように思われた。
『力はいらない、包丁の重さだけで、おろす』
青年の手つきはたどたどしく、店長のそれとは程遠いものではあったが、強い意志のようなものは伝わってきた。
青年の顔を見上げる。
なぜだか懐かしいものを見ている気がした。
こんなに真剣な表情を見るのはどれくらいぶりだろうと思った。
ふと彼が顔を上げた。
引き込まれるように彼の表情を凝視していた私と視線がぶつかった。
私は慌ててカウンターに視線を落とした。
彼もまたチャーシューに視線を戻したらしかった。
私は彼の目を正視する事ができなかった。
青年の姿は私が失ってしまったものそのもののような気がした。
『今日はもう代わろう、今度は玉子の殻剥きを頼む』
私はらーめんをすすっている間中ずっと、青年の姿から目を逸らすことができなかった。
青年はと言えば、バリバリと乱暴な手つきで玉子の殻を破りながら、彼もまた、見事な速さでチャーシューを切り取っていく店長の手元から片時も目を離す事はなかった。
どれくらいの時間が経ったのだろうか。
気がつくと私の器は空になっていた。
『ごちそうさま』
意外な程のか細い声に自分で驚いた。
『ありがとうございました。』
青年の大きな声に、ドンと背中を叩かれた気がした。
ふらつきそうになった。
暖簾をくぐって、ふと返り見た。
紺地に白の毛筆で書かれた文字は『てっぺん』と読めた。
チャーシューを切る彼の表情が一瞬暖簾の上に映し出された錯覚を覚えた。
歩き出してからも、いつまでも青年の姿が頭から離れなかった。
青年の動作や表情のひとつひとつが、私の脳裏に鮮明に焼きついていた。
らーめんの味を全く記憶していない程に気圧されてしまっていたけれど、久方ぶりに何か清々しい光景を目にしたという心持ちがしていた。
———仕事が終わったら、久しぶりに画材屋でものぞいてみるかな。
自社ビルの入り口を通る瞬間、ふと考えた。
心無しか軽くなった足取りのままエレベーターに飛び乗ろうとして、やめた。
一瞬のためらいの直後、エレベーターの横手から伸びる階段の方に回ると、一段飛ばしで登り始めた。(2000)