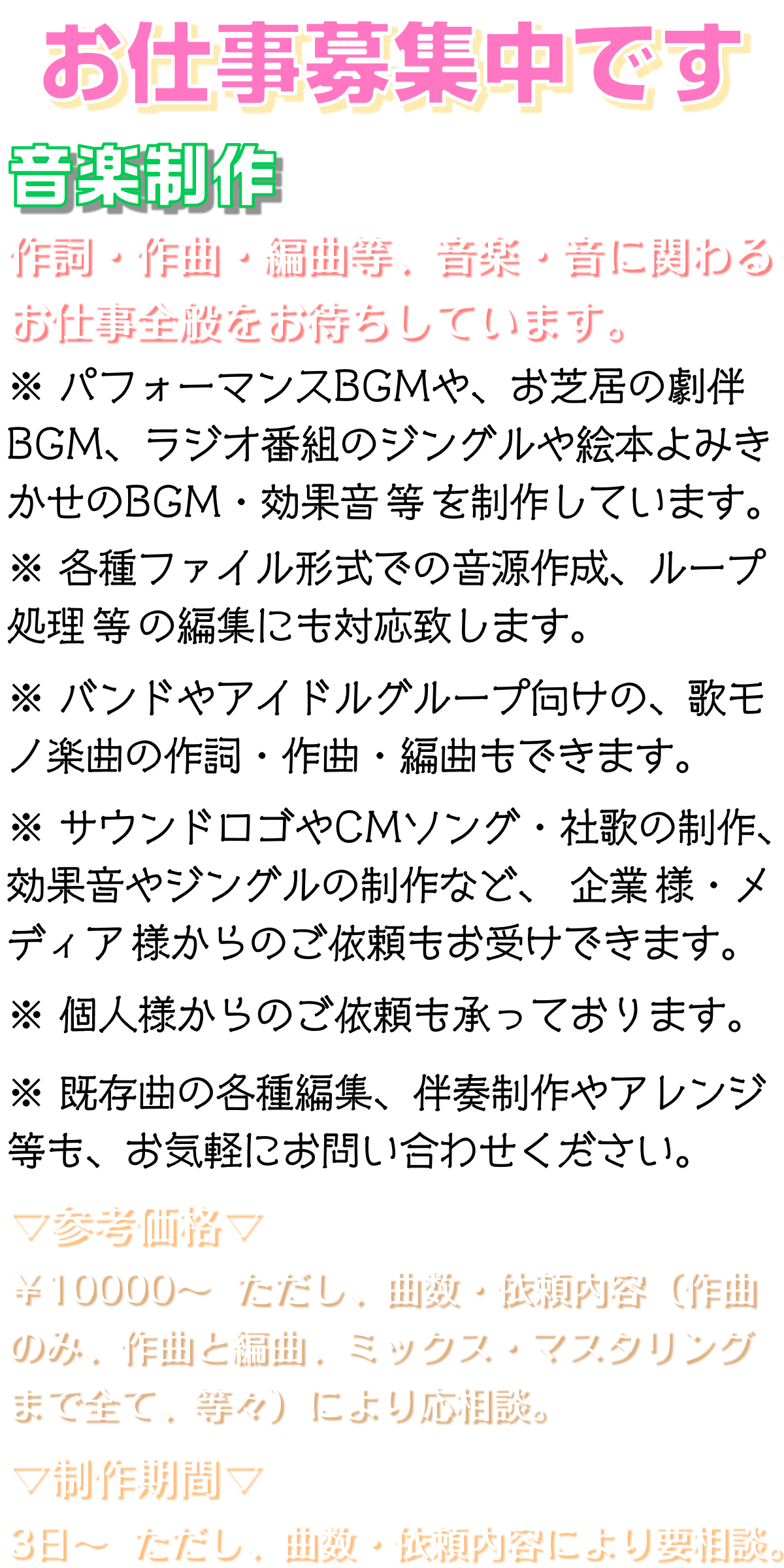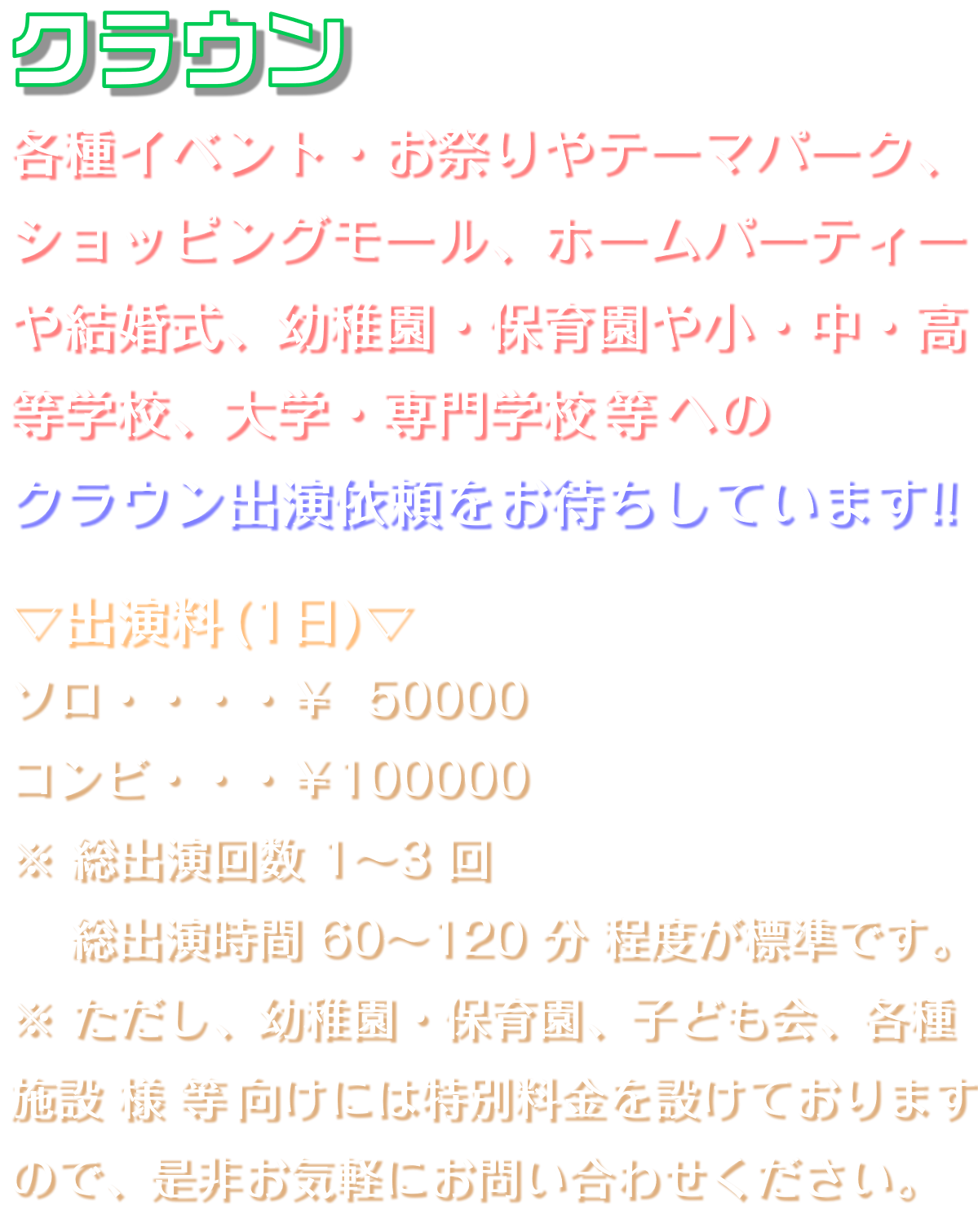最後の授業(小説)

最後の授業(小説)
黒いレースを一枚ずつ重ねていくように、少しずつ暗がりが増えていく。
東向きの窓がひとつ在るだけの化学準備室はもう、参考書を読むには暗すぎる。
蛍光灯を点けるついでに、扇風機を弱にする。
日中はまだ暑いが、朝夕は少しだけ秋めいてきた気がする。
俺は彼女にモル濃度について説明していた。
明日は俺の研究授業、そして、この教育実習を締めくくる最後の授業である。
授業の範囲は中和滴定。
これまでやってきた酸と塩基の定義を実用する大事なところである。
演習問題も結構な量を解いてもらわなければならないだろう。
ところが、である。
放課後の掃除の時間、教室の床をせっせと掃いていた俺に彼女は言った。
化学を基礎から教えて欲しい、と。
何でもモル濃度の概念がわからないという。
モル濃度がわからなければ明日の授業は全く理解できないと言ってもいいだろう。
部活があるという彼女に、夕方までは化学準備室にいる旨を伝えた。
部活が終わる頃には忘れてしまうだろう、とも思った。
いずれにしても、明日生徒達の前でやって見せる演示実験の準備があるから、今日は遅くまで学校に残らなければいけなかったのだ。
予想に反して彼女は、部活を終えた後、約束どおりやってきた。
そして俺は今、彼女のとりとめのない質問にひとつひとつ答えている。
遠くから聞こえてくる生徒達の話し声が、だんだんまばらになっていく。
扇風機が低く唸って彼女の前髪を揺らす。
学生の時もそうだったが、学校とは夜が近づくにつれ妖しさの色を増していくものだと思う。
(これってちょっといいかも)
ゆっくりと流れる時間に浸り始めたその時、澱んだ空気を切り裂いたのは彼女のカバンの中の携帯電話のベルだった。
(おいおいせっかくいい感じだったのにジャマすんなよ・・・)
「もしもし、ユキコ、どうしたの?ふーん・・・えっ、ワタシ?今先生に化学教わってるぅー・・・ん?化学準備室・・・うん、わかった、じゃあねぇー」
ピッ。
「先生、ユキコ達もこれからこっち来るって」
(なにー!!)
やがて、連れ立ってやってきたクラスでも指折りのウルサい、もとい、元気の良い女の子達4人も加わって、化学準備室などという名前のつく場所には到底似つかわしくない騒がしさとなった。
口々に、お腹すいたよー、とか言いながら、銘銘が持ってきた駄菓子を実験台の上に無造作に広げると、いっせいに食べ始めた。
彼女と二人きりでもっとまったりとした時間を過ごすはずだったのに……ヤケになった俺は女子達に交じっておかしをもりもり喰いはじめる。
「先生これ何?」
「わかった、明日の授業で使うんだ」
「あ、やってみてやってみて」
「それよりさぁー、明日やる問題の答え教えてよ、そしたらワタシ手挙げて答えるからさぁ」
「アンタが答えたらあやしまれるに決まってんじゃん」
そうこうしてる間に、彼女達を相手に、演示実験のリハーサルをすることになってしまった。
「先生、ほらそこ、こぼれてるにぃ~、あっ、手が赤くなった、ウー気持ちワルーい」
「そこでさー、あっ、血だ、ワーってやったらウケるらぁ~?」
「ウケるウケる!先生やってぇー!」
(そんなんでウケるわけねぇっつーの)
「先生本当にちゃんと計ってる?ハジメっから決まってるんじゃないのぉー?」
「なんかウソっぽいらぁ~」
「それよりお腹すいたー、先生、帰りになんかおごってよぉー」
(クッソー、こいつら真面目に見る気ねぇーな)
そのうえなかなか実験はうまくいかない。
「もーいいや、リハーサル終わり終わり」
もうどうでもよくなってきた、本番は何とかなるだろう。
「それよりさ、明日の授業のネタ仕込もうかなぁーと思ってんだけどさ、ちょーっと協力してくんない?」
彼女達を見ていたらなぜだか急に悪戯心に火が点いてしまった。
俺は5人の顔を見回しながら悪巧みの計画を話した。
彼女達の目が見る見るうちに生き生きし始める。
そして俺達は計画を実行に移すべく、早速 ❝仕込み❞ に出かけた。
その企てとは……。
翌日の午後。
いよいよ研究授業が始まった。
教室を取り巻く大勢の先生方に、生徒達も少し緊張気味だ。
俺は平常心で授業を展開していく。
無難に進んでいる。
この調子だ。
そしていよいよ中和滴定の演示実験にさしかかった。
ここで失敗したらせっかくの企てが全てパーになってしまう。
腕の見せ所だ。
震える手を抑えつつ、一滴、また一滴、試薬を滴下していく。
まだか、もうそろそろだ、来い来い来い来い、と念じた瞬間、透明な水溶液に淡いピンクが広がった。
値は……
「23mlです」
よっしゃー!ぴったりだ。
5人がニャッとするのが見える。
(先生サバ読んだんじゃないの?)
(本当にぴったりだったんだって)
「それじゃこの値を使って計算して、濃度不明だったシュウ酸水溶液のモル濃度を求めてみてください」
机間歩行しながら、カキザワが座る一番後ろの席に近づき、さりげなく背後に回った。
ヤツは伝統ある應援團の次期副團長で、俺がこの高校の應援團のOBと知ってからというもの、誰よりも真面目に授業を受けるようになった。
かわいい後輩、そして、最も信用できる男だ。
カキザワ、頼む、がんばれ、早く解いてくれ。
えーと……うん、よし、合ってる。
お前なかなかできるじゃねえか。
全ては計算通りだ……。
「はい、うーんと、それじゃカキザワ君に、前でやってもらおうかな」
今にも吹き出しそうなのを必死でこらえている5人。
そんなことに気づくはずもなく、カキザワは真剣な表情で、ノートを片手に計算式を黒板に写している。
他の生徒も問題を解くのに夢中だ。
俺は勝利を確信した。
カキザワが解答まで板書し終わって、席に戻った。
他の生徒も大多数が解き終わるのを確認した後で、みんなに呼びかける。
「はい、カキザワ君の答えは、5.75×10 mol/l ということですが、みんなはどうだった?
同じになった?
5.75×10 mol/l かな?」
目のあった生徒が頷いてくれる。
大多数の生徒が解けている様子だ。
「じゃ実際の濃度はどうだったのかというと・・・」
ここで一瞬、豆鉄砲をくらったハトのような表情をしてみせる。
「あれ、おかしいな、メモが無くなっちゃった、あれれ」
大事な研究授業なのに……生徒たちの表情が一瞬にして強ばっていくのがわかる。
嗚呼、みんななんていい生徒達なんだろう、そんな生徒の心を弄ぼうとしている俺ってなんて悪いヤツなんだろう……
「あっ、ひょっとしてカキザワ君、俺の答え持ってっちゃったんじゃない?」
「いえ、持ってってませんよ」
「いや、カキザワ君が持ってったとしか考えられない」
「えっ、えー!」
突然罪を負わされて焦るカキザワ。
これは只事ではないと、先生方もざわざわし始める。
「いや、そうだ、きっと踏んづけてスリッパの裏にくっつけて行っちゃったんだ」
「えっ?でも、ボク、スリッパ?エー!」
パニクったカキザワが意味不明なことを口走る。
ごめんよカキザワ。
「じゃスリッパの裏に答えがついてないか見てみてよ」
訳がわからないという表情で、それでも言われるままにスリッパを脱ぎ、裏返すカキザワ。
次の瞬間、
「アッ!!」
それを覗き込んだ周りの生徒も
「アッ!!」
しばらくして驚きが笑いに変わる。
何事かとざわざわしていた先生方も椅子から腰を浮かせて覗き込んだその直後、大爆笑をはじめた。
それを見た俺は、自信たっぷりにたずねる。
「カキザワ君、答え、あった?」
「あっ・・・はい、ありました!」
「5.75×10 mol/l で、合ってる?」
「はい、合ってます!」
「みんな、聞こえた?カキザワ君がこれで合ってるってさ」
シャイなカキザワ君は顔から火が出そうだ。
カキザワの周りの生徒は大喜びで囃したてる。
まだ何が起きたのかよくわからず、思わず立ち上がって後ろを振り返っている生徒もいる。
驚いて口が開いたままになってしまっている生徒もいる。
でも一番驚いたのはカキザワだろう。
だって、いつもと変わらず履いていた自分のスリッパの裏に、いつの間にか、小さく、しかしはっきりと、「5.75×10 mol/l」と記されていたのだから。
授業後、ひそかに5人の仕掛け人達と成功を称えあったことは言うまでもない。
そして掃除の時間、お礼とお詫びをしようとカキザワに声を掛けた。
「先生、答えいつの間に書いたんですか?びっくりしましたよ」
笑いながら話すカキザワはまんざらでもなさそうだった。
「カキザワ君が黒板に答えを書いてる間だよ」
「エー!でもボクずっとスリッパ履いてましたよ」
実は前の日の夜、5人の女の子達と一緒に、守衛さんの目を盗んで、こっそり下駄箱で書いたんだよ、とは言わなかった。
❝仕込み❞ のことは、あの5人と、俺だけの秘密だ。
「いやぁ、カキザワごめんよ、お前をダシに使っちゃってさ。
でもおかげで笑い取れたよ。
お詫びにスリッパ新しいのプレゼントさせてよ」
「や、いいっすよ、このスリッパ、これからも使いますから。
テストでわからない問題が出た時、裏返したらまた答えが書いてあるかもしれないじゃないすか」
鈍行を選んだのは、もう少し長く教育実習をやっていたかったという気持ちの表れだったのかもしれない。
しかし、それは許されない。
明日からはまた、卒論に追われる東京での生活が待っている。
窓の外を飛び去って行く風景を目で追うことにも飽きて、実習の記念に、クラスのみんながくれた色紙を取り出す。
無秩序に踊っているカラフルな文字達の上を、何の気なくゆっくりとうつろっていた視線が、色紙の右端でとまった。
それは、ちょっと気になる例の彼女の字だった。
『モル濃度、実は理解してました。先生ごめんね』
「お母さん、富士山だよ富士山」
「本当、きれいね」
顔を上げると、左手の窓いっぱいに広がった薄茶色の肌が、少し傾き始めた日の光を浴びて、眩しく輝いているのが見えた。
ひょっとすると、本当にハメられたのは俺の方だったのかもしれないな、そう思うと、なんだかおかしくて、富士山に向かって一人でニヤニヤした。
東京に着く頃には日も暮れている事だろう。
俺は少し眠ることにした。
生徒達の顔をひとりひとり頭に浮かべながら、ゆっくりと瞼を閉じた。(1998)