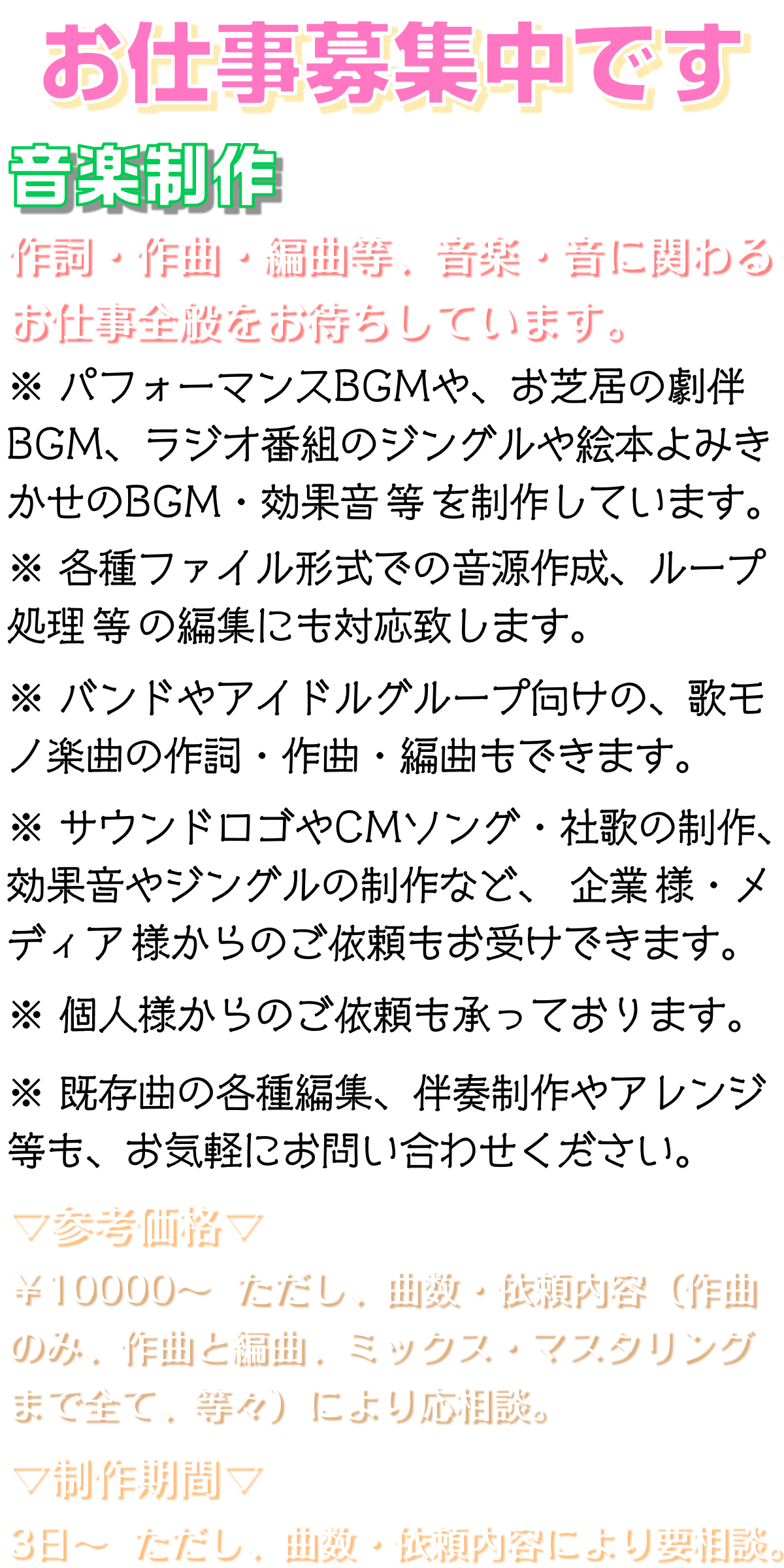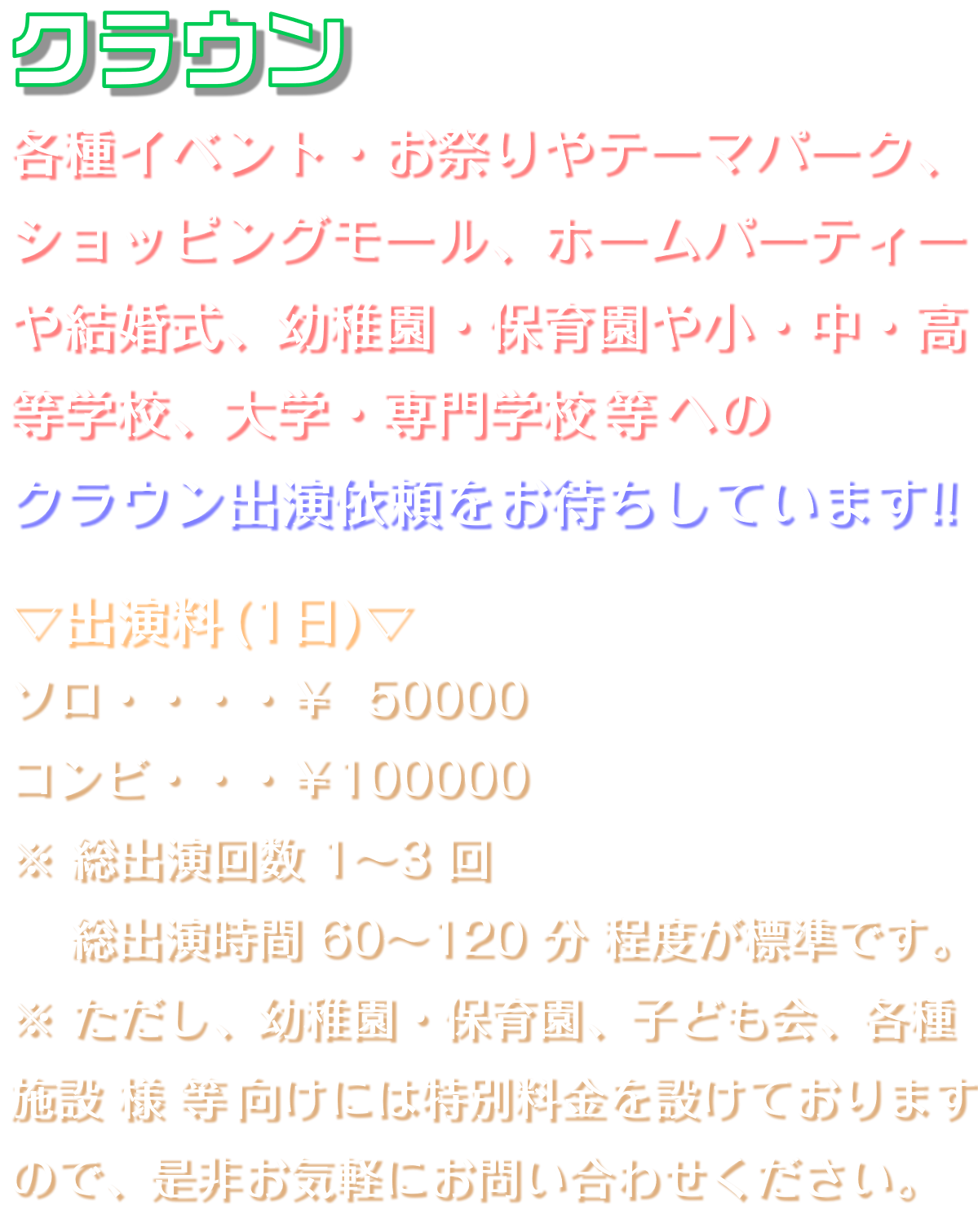拍手(小説)

拍手
今夜もその男はやってきた。
彼はいつものように私の前を静かに通り過ぎると、これもまたいつものように私の真横に位置する噴水の石畳にゆっくりと腰かけた。
そこが彼の指定席だった。
この公園で路上ライブを始めてはや三か月。
初めは遠巻きに見ていた人達も徐々にその距離を縮め、今では演奏の合間には車座になって話し込む程の仲になった。
けれど彼だけは違う。
ライブを始めた当初から、彼はいつもそこにいた。が、絶対に私達の輪の中に入ってこようとはしなかった。
それでも彼は、いつもそこにいた・・・。
初めのうちは、恋人と待ち合わせでもしているのだろう、と思っていた。
しかし、彼の待ち人はいつになっても姿を現さなかった。
毎回私が演奏を終えるのと同時に何処かへ消えてしまうのも不可解だった。
街灯を背にする彼の顔は暗がりの中でぼんやりとして、表情を伺わせないどころか無気味な印象さえ漂わせていた。
何ら害をもたらす訳ではなかったが、私は苛立った。
微妙な距離感を保ったままの彼が、今夜もまたそこにいる・・・。
『今夜こそはっきりさせてやる』
歌いながら横目で彼を観察する事に決める。
私の歌を聴いていると確信できる理由を探した。
しかし彼は、リズムに合わせて身体を動かす事も、歌詞を口ずさむ事もなかった。
こちらに関心を向ける素振りを一切見つけられぬまま、一曲歌い終わってしまう。
(違ったのか)
わずかな期待が裏切られたと思ったその時、彼の両手が二度、三度、小さく動くのが見えた。
『あっ』
間違いなかった。
とても微かで、ゆっくりと、遠慮がちではあったが、紛れもなかった。
それは拍手だった。
彼は拍手していた。
私の歌に拍手していた。
これまでも彼はきっと、私の気づかないところでずっと、拍手を送り続けてくれていたに違いない。
知らなかった。
突然彼にお礼を言いたい衝動にかられた。
しかし今更彼に、どんな言葉をかけたらいいのだろう。
とその時、彼は足早に歩み寄ると私の足元にビニールの包みを一つそっと置いた。
飲み物の差し入れだった。
(今しかない)
黙って立ち去ろうとする背中に向かって声を掛けた。
夢中だった。
『あの・・・、いつもどうもありがとう。』
この時やっとの思いで私が発する事のできた言葉はこれだけだった。
驚いた事に、彼には日本語が通じなかった。
彼は韓国人だった。
彼の英語交じりの片言の日本語が、彼が宣教師として日本に来ている事、自分も音楽を好み、作曲もしている事、そして、歌詞の意味はわからないけれど私の歌がとても好きであると言う事を伝えてくれた。
明るい光の下で見る彼の目はとてもやさしかった。
徐に私のギターを手に取ると、彼はゆっくりとしたストロークでFのコードを奏でた。
讃美歌を歌う彼の声は穏やかで、脳味噌の奥の方をくすぐられている気分だった。
包み込むようなアーメンの響きの中で私は、言葉や国境や民族や宗教や、全てを超越してしまうものの存在について考えていた。
そして讃美歌が終わった時、私は一心に彼に拍手を送っていた。
彼の三か月分の拍手には、到底及ばないかもしれないけれど。(2000)